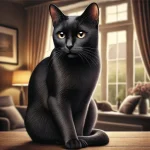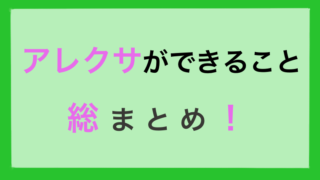新年度が始まり、慌ただしくもフレッシュな気分で過ごしていた4月。
ところがゴールデンウィークを過ぎる頃から、なんとなく気力がわかなくなる……。
そんな状態を「五月病」と呼ぶことがあります。
実は私も新入社員の頃、朝ベッドから起き上がれず「これって五月病かも?」と感じた経験がありました。
そこで本記事では、五月病の症状や原因、具体的な克服方法をまとめます。
「新入社員 五月病 体験談」を知りたい方や「五月病 いつまで 続くの?」と不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
五月病とは?──医学的には「適応障害」の一種かも
五月病の定義と背景
五月病とは医学用語ではなく、主に新卒社員や異動したばかりの人が、
連休明けに心身の不調を感じる状態を指す俗称です。
正式には「適応障害」に近いとされ、仕事内容や人間関係など新環境にうまくなじめないストレスが原因となりやすいです。
症状の例
-
朝起きるのがつらい
-
仕事へ行く気力がわかない
-
なんとなく憂うつ
-
強い疲労感や身体のだるさ
-
不安や焦りで夜眠れない
こうした症状は一過性のことが多いですが、
放っておくと長引いたり「適応障害」として本格的な治療が必要になる場合も。
「五月病 適応障害 違い」が気になる方は、
症状が長期化・重症化すれば専門的なケアが必要と心得ましょう(出典: https://rocketnews24.com/)。
五月病の原因──「新環境の疲れ」が連休明けに噴き出す
ストレスは真面目な人ほどため込みやすい
新社会人や異動者は、4月から新しい仕事や人間関係にさらされます。
慣れない環境で気を張り詰めていた結果、連休明けに気持ちが切れてしまうのです。
とくに几帳面・完璧主義・責任感が強い人は要注意。
「自分がダメなんだ」と思い込み、さらにストレスを抱え込むケースもあります。
「五月病 予防 新社会人」の視点では、適度に周囲へ頼る姿勢が大切だといわれています (出典: https://ashitano-jinjibu.jp/)。
新入社員 五月病 体験談は決して珍しくない
2025年の国内調査でも、社会人の3割以上が五月病を経験したと報告されました。
さらにそのうち8割近くが「強い無気力を感じた」と回答。
こうしたデータからも「自分だけが弱いのではない」「誰にでも起こり得る」ことを知っていただきたいです。
正直、最初は「私ってこんなに打たれ弱かったっけ?」と落ち込みましたが、
後から調べると意外にも周りで同じ悩みを抱えている人が多かったんです。
五月病を乗り越える4つの方法
1. まずはしっかり休息をとる
-
疲れ切った心身には睡眠と休養がいちばん
-
有休取得や週末のリフレッシュで英気を養う
-
「休むのも仕事のうち」という意識でOK
実際、2019年のアンケートでも「十分休んだら自然に治った」という声が最多でした。
無理をするとさらに悪化するので、休むことに罪悪感を持たずに過ごしましょう。
2. 趣味や楽しいことに時間を使う
-
仕事以外での楽しみを確保
-
お笑い番組や映画を観て笑う
-
音楽・読書・ゲーム……何でもOK
私も新卒時代、一度まるまる1日ゲームに没頭してみました。
最初は「こんな時に遊んでいていいのかな…」と感じたものの、
終わった後は嘘のように頭がスッキリ。
そのおかげで翌週から少し前向きになれました。
3. 生活リズム・食事を見直す
-
夜更かしをやめ、朝少し早起きして散歩
-
朝日を浴びて体内時計を整える
-
栄養バランスのとれた食生活を意識
2025年のメンタルケア調査では「体を動かしながら栄養面を整えると回復が早い」という傾向が示されています。
わたし自身、連休に崩れがちだった生活サイクルをゆっくり戻していくうちに、気持ちも落ち着きました。
4. 軽い運動を取り入れる
-
通勤時に一駅分歩く
-
ヨガやストレッチで血行を促す
-
週末に軽くジョギングやジム通い
運動すると「なんだか気分が前向きになる」と実感する方も多いですよね。
体だけでなく心のリフレッシュにもなるので、「五月病 克服 方法」としておすすめです。
また、六月病(6月病)とはと気になる方もいますが、
5月にうまくストレスを解消しないと、6月以降も慢性的な疲労を引きずる例があるようです。早めにケアしておきましょう。
一人で抱え込まない──相談できる相手を探そう
話すだけで意外とラクになる
-
信頼できる先輩や同期に相談
-
家族・友人でも構わない
-
「話すことで頭が整理される」効果あり
「五月病 相談 相手」に迷う方は、まず身近なところから声をかけてみてください。
意外と「実は自分も悩んでいた」と打ち明けてくれる人がいるかもしれません。
孤立しないだけでも心の負担は大きく減るはずです。
プロの力を借りることも視野に
-
会社のEAP(従業員支援)や産業医
-
メンタルクリニックや心療内科を受診
-
1ヶ月以上つらいなら専門家へ
大阪府医師会も「五月病かな?と思ったら早めに相談を」と呼びかけています。
なかなか症状が改善しない場合は、遠慮なくプロを頼るのも大切。
適応障害やうつ病のような状態になる前にケアできれば、回復もスムーズです。
「五月病 症状 チェックリスト」などでセルフチェックするのも有効ですよ。
再発防止!五月病にならないための日頃のケア
オンオフのメリハリを意識
-
平日も小さな楽しみを持つ
-
仕事終わりにお気に入りカフェへ
-
週末は映画や趣味でリラックス
同僚とのコミュニケーションを増やす
-
雑談や相談が気軽にできる関係を築く
-
孤立感がメンタル不調の大きな要因に
-
「遠慮せず頼ってOK」というマインドを育む
完璧主義を手放す
-
「まあ、いいか」を口癖にする
-
完璧にやろうとすると心が疲弊
-
認知行動療法などで考えグセを柔軟に
私も「自分が頑張らないと…」という想いが強く、
失敗できないと身構えすぎていた時期がありました。
でも「とりあえず7割くらいの出来でいいか」と思ったら、
ストレスが軽くなりむしろ成果が上がったこともあります。
まとめ
五月病は、新しい環境に適応する過程で誰にでも起こり得る心身のスランプ。
「自分だけがダメ」ではありません。
一過性で済むことも多い一方、放置すると深刻化するリスクも否定できません。
大切なのは「休養を取る」「趣味に没頭してみる」「周囲に相談する」など、
早めに手を打ってストレスを解消することです。
5月をしんどいまま乗り切ると、6月以降のやる気やパフォーマンスにも影響しがち。
「五月病 いつまで 続くのかな?」と感じたら、焦らず対策を始めてみてください。
無理せずあなたのペースで、少しずつ気持ちをリセットすれば、
5月を乗り越えた自分はきっと一回り成長しているはずです。
どうか今は自分をいたわって、前を向いていきましょう。