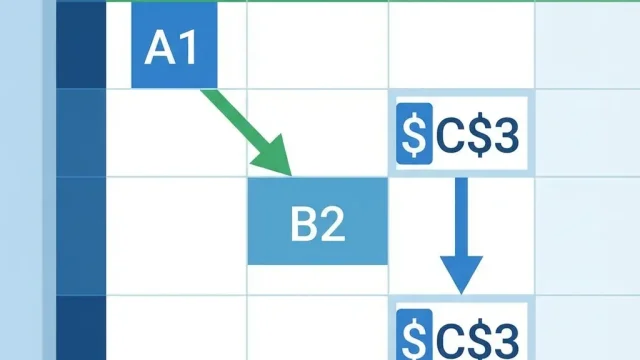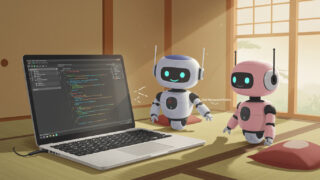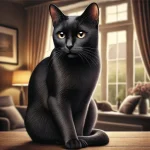新型コロナウイルスの感染拡大が世界を揺るがした2020年初頭。企業や組織は一斉に在宅勤務へ移行することを余儀なくされました。
正直、当時は「まさか、こんなに急にリモートワークが一般化するなんて」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
そんな中で爆発的に利用が増えたZoomやMicrosoft Teamsといったコラボレーションツールは、私たちの働き方を大きく変えました。
この記事では、リモートワーク導入が急激に進んだ背景や、主要ツールの進化、そして実際の生産性への影響について深掘りしていきます。
短期間で驚くほど進化したリモートワーク技術を振り返りつつ、今後の働き方におけるヒントを探してみましょう。
パンデミック宣言とリモート移行
2020年初頭のロックダウン
世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスをパンデミックと宣言し、多くの国で外出制限や企業活動の停止措置が取られました。
日本でも緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出が自粛されることになります。私は当時、まさか「明日から全員在宅勤務」という決断を経営陣が下すとは思っていませんでしたが、実際はそういう企業が続出しました。
通勤が困難な状況でも業務を続けるため、多くの企業が急ピッチでリモートワーク環境を整備します。
ネットワークやセキュリティの課題はもちろん大変でしたが、「やらないと仕事が回らない」という切迫感が企業を動かしました。
多くの企業が急遽リモート導入を決断した背景
- 在宅勤務しか選択肢がないほど、感染拡大が深刻
- 国や自治体から在宅勤務推奨の呼びかけが相次いだ
- 通勤リスク回避と企業イメージ保持のための措置
これまでリモートワークに二の足を踏んでいた企業も、コロナ禍を機に体制を整えざるを得ない状況に追い込まれました。
「正直、こんなに早く在宅シフトできるとは思わなかった」と感じた方も多いはずです。ここで本格導入した企業が多かったことが、後のリモートワーク定着に大きく寄与しました。
主要ツールの爆発的普及
Zoom・Teamsのユーザー数の急増
コロナ禍前から存在していたオンライン会議ツールの代表格といえば、ZoomやMicrosoft Teamsでしょう。2020年初頭、在宅勤務の広がりに合わせて爆発的なユーザー増を記録しました。
- Zoomの月間アクティブユーザーが一時7億人を超えたとの推計
- TeamsもOffice 365との連携を強みに一気に普及
私自身も、初めてZoomを使ったときには「こんなに画質と音声が安定しているのか」と驚いたのを覚えています。
ただ、それが一夜にして世界中のユーザーに支持されるとは思いませんでした。
企業研修や学校のオンライン授業にも積極的に取り入れられ、あっという間に「Zoom会議」という言葉が定着していきます。
トラブル事例(Zoom爆撃など)とセキュリティ対策の進化
リモート会議の急拡大は、多くのメリットと同時にトラブルも生みました。
特に初期に問題視されたのが、いわゆる「Zoom爆撃(Zoom Bombing)」です。パスワード設定の甘さなどを突かれて不正侵入者が会議を荒らす事件が報告されました。
- 「知らない人が急に画面共有で不適切画像を投げ込む」
- セキュリティ専門家からZoomの暗号化方法に懸念の声
こうした事件を受け、Zoomをはじめ各社がセキュリティ強化に乗り出しました。会議へのパスワード設定が標準化され、ホストが参加者を制御する機能の拡張、エンドツーエンド暗号化への取り組みなどが相次ぎ導入されました。
Microsoft Teamsも同様にセキュリティ機能を強化し、IT管理者がリモート会議のアクセス権限を細かくコントロールできるようになっています。
これらの対策は、正直なところ「もっと早く実装されていれば…」と思う部分はありましたが、ユーザー数が激増する中、メーカー側も短期間でアップデートを進めたのは相当な努力だったと思います。
生産性と働き方への影響
初期懸念(生産性低下、不安定な通信環境など)
緊急事態宣言下では、多くの企業が「リモートワーク=生産性が落ちるのでは?」と心配していました。
たしかに最初は、在宅勤務に不慣れな社員が多く、接続トラブルや社内コミュニケーションの停滞が目立ちました。
また、狭い部屋や家族との同居環境で仕事に集中しづらいという問題も大きかったと思います。
- VPN接続が夕方に集中して回線が落ちる
- 子どもが横で騒ぐため会議に集中できない
「正直、こんな状況でちゃんと仕事ができるの?」と戸惑う声は少なくなかったでしょう。
しかし、少しずつオンライン会議のやり方やチャットツールの活用が浸透していくにつれ、意外とリモートワークの生産性が保たれる(あるいは向上する)事例が現れ始めました。
調査データから見る実際の効率(約70%が同等以上と回答)
パンデミック後、米国を中心にリモートワークの生産性についてさまざまな調査が行われました。
中でも注目されるのが「約70%の労働者がリモートワークで同等以上の効率を感じる」という結果です。
これは私もかなり意外でしたが、ツールと環境さえ整えれば意外に仕事は回るものなのです。
- 通勤時間がなくなり、集中作業の時間確保が可能
- 対面会議が減り、無駄なミーティングが削減
もちろん業種や職種によって差がありますが、リモートワークにポジティブな反応を示す企業や個人が増えていく結果となりました。
インフラ整備とサポート
VPN帯域問題とクラウドプロキシ(Zscaler等)の需要増
リモートワークが急拡大した一方で、企業のIT部門はVPN帯域問題に頭を抱えることとなります。
全社員が同時にVPNへアクセスしようとすると、回線がパンクしてしまうのです。そこで注目を集めたのが、クラウドプロキシやセキュリティを担保するサービスの導入でした。
- Zscalerなどクラウドベースのセキュリティプラットフォームが急成長
- VPNを介さずにクラウドサービスへアクセスできる仕組みを整備
正直、IT部門からは「そんなに早く大勢がリモートに移るとは想定外」という声が多数聞かれました。
けれども、クラウドプロキシを導入することで本社ネットワークへの負荷を軽減し、ユーザー体験の向上にもつながった企業が多かったようです。
リモートワークを支えた政府・自治体・企業の取り組み
各国の政府や自治体も「在宅勤務を支援しよう」と動き出しました。
日本でもテレワーク補助金や支援策が検討・実施され、在宅勤務用の設備購入費や通信費のサポートが始まった事例があります。
また、急遽在宅勤務になった社員へ、企業がノートPCを貸与したり、Wi-Fiルーターを配布する動きも加速しました。
- 補助金や助成金でITツール導入費用を部分的にカバー
- 一部企業は社員に在宅勤務手当を支給し、自宅設備を整える後押し
こうした取り組みは「正直、もう少し早ければスムーズだったのに…」と感じる部分もありますが、未曽有の事態に対応するうえでは一定の効果があったといえるでしょう。
まとめ
2020年から2021年にかけてのリモートワーク急拡大は、まさに歴史的な大転換期でした。
パンデミックという緊急事態に対処するため、ZoomやTeamsなどのオンライン会議ツールが一気に普及し、セキュリティやネットワーク技術も短期間で大きく進化しました。
- 「大丈夫かな?」と不安が先行していた企業も多数
- 結果的に、生産性が維持・向上できたケースが増加
- VPNの帯域問題や在宅環境整備の課題が顕在化する中、クラウドサービスへの需要が急伸
このような流れの中で、多くの企業が「リモートワークって意外といけるんだ」と実感し、今後の働き方を再定義するきっかけとなりました。
正直、私もこれほど急激に状況が変わるとは思いませんでしたが、振り返ると「社会の柔軟性も捨てたもんじゃないな」と感じます。
次回は、リモートワークが定着した後のハイブリッドワークや、オフィス回帰の動きについて見ていきます。
コロナ禍を経た今、私たちの働き方は一体どこへ向かうのでしょうか。今後も続々と登場する新技術や、新たな組織文化のトレンドを追っていきたいと思います。