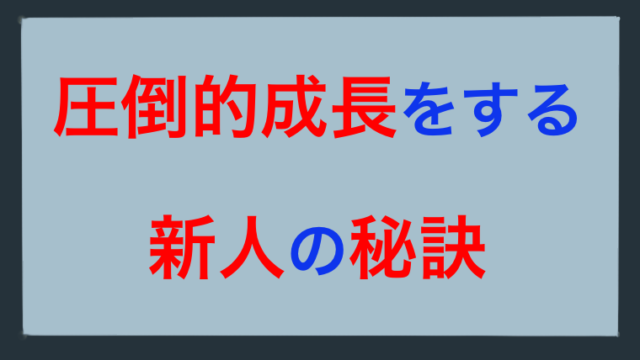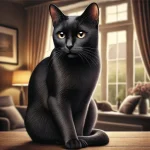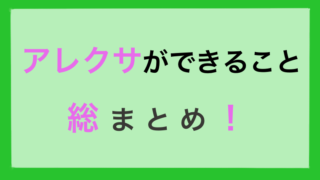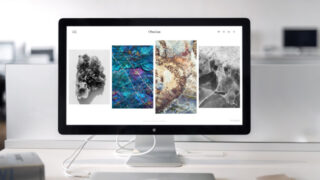初めての社内プレゼンは、しっかりとしたプレゼンテーション準備・練習方法を押さえておくだけで大きな安心感につながります。慣れない場で話すのは誰でも緊張するもの。だからこそ事前の準備こそが成功のカギです。
ここでは、社内プレゼン初心者の方に向けて「目的の整理」から「本番直前のチェックリスト」まで、4つのステップで解説します。オンライン発表にも役立つ最新情報やメンタル面のコツも併せてご紹介します。ぜひ参考にして、あなたのプレゼンをスムーズに進めてくださいね。
なぜプレゼン準備が成功のカギ?初めての社内プレゼンで失敗しないために
社内プレゼンは、自分の提案を上司や決裁者に通す重要な機会です。限られた時間の中で相手を納得させ、意思決定を引き出すには、やみくもに資料を作って話すだけではうまくいきません。
実はある調査で、社会人のおよそ6割が「プレゼンは苦手」と感じているという結果もあります。苦手意識を持ったまま本番に臨むと、焦りや緊張で本来の内容が十分に伝わらないかもしれません。しかし裏を返せば、しっかりと準備すればその不安は必ず軽減できるということ。初心者でも順序立てて準備し、練習を積めば本番に自信を持って話せるようになります。
ステップ1: プレゼンの目的と聞き手を押さえる【準備編】
1)何のためのプレゼンか、目的を明確にする
はじめに「自分はこの社内プレゼンで何を実現したいのか?」をはっきりさせましょう。たとえば、社内予算の承認、上司への新企画提案、チームメンバーへの報告など、目的が変われば伝え方も異なります。
社内プレゼンの初心者ほど、まずは「どうしたら納得してもらえるか」をシンプルに考えることが大切です。具体的には、「結論」を鮮明にしてから理由や根拠を並べる流れが分かりやすいでしょう。
2)聞き手の関心や期待を考える
聞き手の置かれた立場や興味を想像すると、プレゼンの方向性が見えやすくなります。上司なら「費用対効果」や「リスク」に関心が強いかもしれません。同僚や他部署への説明なら、具体的なメリットが伝わるかどうかがカギです。
また、最近はオンライン会議でプレゼンするケースも増えています。対面かリモートかによって、機材や接続環境など準備内容は変わるので、最初の段階でどちらのスタイルかを確認しましょう。
ステップ2: 資料作成と台本づくりのコツ【準備編】
1)資料(スライド)は「シンプル&伝えたいことを一つ」に絞る
「見やすく分かりやすい」を心がけるだけで、初心者でもぐっと伝わりやすくなります。1枚のスライドには1つのメッセージに絞り、複雑な箇条書きは避けましょう。社内プレゼンを成功させるコツとしては、結論と根拠をセットで示す“ロジカル構成”が有効です。
-
色は使いすぎない
強調色を1色決め、それ以外はモノトーンをベースにすると統一感が出ます。 -
フォントサイズは大きめ
対面なら後方の人にも見えるように、オンラインなら共有画面で読める程度に余裕を持った文字サイズを。 -
オンライン向けは16:9比率推奨
画面共有の場合、ほとんどのPC画面がワイド(16:9)なので最適化が必要です。
さらに、通信が不安定な状況を考慮してアニメーションや動画を多用しすぎると動作が重くなる可能性も。プレゼンの事前準備チェックリストに「ファイル容量の確認」を入れておくと安心です。(出典: https://goodpresen.jp/column/presentation-preparation-checklist)
2)プレゼン原稿の作り方とコツ
資料と同時に「ここでは何を話すか」をまとめた台本(原稿)も用意しておくと、プレゼンの緊張を克服する方法として効果的です。話す内容が頭の中で整理できるので、本番で焦りにくくなります。(出典: https://moved.co.jp/blog/tsutawaru-presentation-script)
ただし一語一句を読み上げるのは避けたいところ。自然に語れるようにするため、プレゼン 原稿 作り方 コツとしては下記のポイントがあります。
-
スライドをめくるタイミングやつなぎ言葉をメモ
「続いては…」「次のスライドは…」などの接続フレーズを入れると流れが途切れません。 -
台本は“見返しやすい”形に
B5サイズで印刷して製本したり、A4紙をホチキスで綴じるなど、緊張で手元が乱れてもバラバラにならない工夫を。 -
完全な棒読みはNG、要点のキーワードを並べるイメージ
「原稿を持つ安心感」が大事なので、細かい言い回しにこだわりすぎず、要点を押さえて自然に話せる構成にしましょう。
3)最新ツールを活用する選択肢も
今はAIを使ったプレゼン資料の支援や、音声コーチングツールが普及しています。資料構成のアイデアや話し方のテンポを分析してくれるサービスもあるため、時間のない方はこうしたツールを試してみるのも手です。もちろんアナログでも十分対応できますが、「まずはAIに構成案を提案してもらい、それを取捨選択しながら自分の言葉に落とし込む」など、うまく使えば準備の効率アップが期待できます。
ステップ3: 本番さながらの練習をしよう【練習編】
1)リハーサルで本番を想定する
「ぶっつけ本番」は大きなリスク。初心者ならなおさら、プレゼン リハーサル のやり方をしっかり身につけておきましょう。たとえば社内の先輩や信頼できる同僚に模擬発表を聞いてもらい、時間配分や話のわかりやすさをチェックしてもらうのがおすすめです。(出典: https://www.signfujita.co.jp/knowledge/beginner_inhouse_presentation)
-
制限時間内に収まるか
ストップウォッチやスマホのタイマーを使い、何分で終わるかを測定しましょう。 -
声の大きさ・抑揚は適切か
小声すぎないか、早口になっていないか、外部から客観的に見てもらうとより明確になります。 -
姿勢や目線の移動
対面なら聴衆全体に視線を、オンラインならカメラを見るなど、場に応じたコツを練習します。
2)一人でできるプレゼンの練習方法:録画チェック
「練習相手がいない」「恥ずかしくて人前でリハーサルできない」という方におすすめなのが、スマホやPCで自分のプレゼンを録画してみる方法です。
最初は見るのが照れくさいですが、意外と「こんなに早口だったのか」「姿勢が崩れている」といった改善ポイントがわかります。撮影→再生→改善→再撮影…というサイクルを数回回すだけでも、かなり自信がついてきます。
3)緊張を和らげるマインドセット
プレゼンの緊張 克服 方法としては「うまく話そうとしすぎない」「多少詰まってもOK」と自分に許可を与えることが大事です。(出典: https://allabout.co.jp/gm/gc/442222)
-
「一語一句完璧に言わねば」と考えるほど緊張が高まる
-
「ある程度かんでも仕方ない」と割り切ると、むしろ自然な調子になる
適度な緊張は集中力を高める効果もあるので、「これは良い緊張感だ」と前向きに捉えてみましょう。
ステップ4: 当日までにやっておきたい最終チェックリスト【準備&練習編総まとめ】
最後に、プレゼンの事前準備チェックリストを仕上げておくと当日慌てずに済みます。ここでは対面・オンラインの両方を想定してリスト化しました。(出典: https://goodpresen.jp/column/presentation-preparation-checklist)
対面プレゼン向け
-
□ 会場の下見は済ませたか
-
□ プロジェクターやPCの接続テストをしたか
-
□ スライドや表は画像化して表示崩れを防止
-
□ プレゼン時間をストップウォッチで確認したか
-
□ プレゼン 質疑応答 の準備として想定Q&Aを整理
-
□ 資料の印刷部数や配布タイミングの確認
オンラインプレゼン向け
-
□ 通信環境(Wi-Fi有無、回線速度)の確認
-
□ マイク・カメラ・画面共有機能の事前テスト
-
□ 画面に不要な通知や個人情報が映らない設定
-
□ ファイル容量の圧縮・配信テスト
-
□ Q&Aでチャット機能を活用する段取り
直前にもう一度、自分が用意したプレゼン原稿 作り方のコツを思い出し、落ち着いておきましょう。どちらの形式でも、社内プレゼン 成功 コツの根本は「相手目線の内容」と「十分なリハーサル」に尽きます。
まとめ
プレゼンは準備と場数で必ず上達します。最初は誰しも失敗を恐れますが、今回ご紹介した4つのステップを踏めば、社内プレゼンの初心者が準備するときでも十分に対処できるはずです。
大事なのは「相手が聞きやすいように」「焦らずリハーサルする」こと。オンラインであれ対面であれ、聞き手目線の内容づくりと念入りなリハーサルを徹底すれば、初めてのプレゼンでもきっと伝わります。次のプレゼンに向けて、今日から少しずつ準備を始めてみませんか?